「現場をまとめる職長になりたいが、未経験でも目指せるのか?」と悩んでいませんか?
本記事では、未経験から職長を目指すために必要なキャリアの積み方、取得すべき資格、現場で求められるスキルやマインドセットまでを丁寧に解説します。建設業界でキャリアアップを目指す方に向けて、信頼されるリーダーになるための具体的な道筋をお伝えします。

経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月20日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
週休二日相当の休みやすさもあり、プライベートとの両立もしやすい職場です。
単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
まずは職場見学で現場を体感してみてください。後輩育成にやりがいを感じていた方、きっと共感いただける環境です。
詳しくは職長要項へ
職場見学・応募はこちら
未経験者が目指すべき“理想の職長像”とは
 現場が求める職長の人物像と評価ポイント
現場が求める職長の人物像と評価ポイント
未経験から職長を目指す場合、まず理解しておきたいのが「現場で評価される人物像」です。職長は作業の指示を出すだけでなく、チーム全体の士気や現場の安全にも関与する重要なポジションです。
そのため、評価されるポイントは単なる技術の高さだけではありません。以下のような人物が、現場で職長として信頼されやすい傾向にあります。
- 報告・連絡・相談がしっかりできる人
- 怒らず冷静に対処できる人(話しかけにくさが情報共有を妨げる)
- 時間やルールを守るなど、現場の基本を徹底している人
- 年下・年上問わず、周囲と良好な関係を築ける人
- 人の動きをよく観察し、危険に気づける人
- 自分が指揮して現場を温めて仕上げていく事が好きな人
未経験者でも、これらの姿勢を持ち合わせていれば、周囲から「任せてみたい」と思われる可能性は高まります。
技術力だけでなく信頼・対応力が問われる理由
「職長は現場で一番仕事ができる人」と思われがちですが、実際にはそれ以上に「信頼される人」であることが重視されます。
現場には様々な立場の人が集まり、意見がぶつかる場面も少なくありません。そんな中で職長が感情的に振る舞ってしまえば、現場の空気が一気に乱れてしまいます。
だからこそ、技術よりも先に「この人の指示なら納得できる」と思わせる安心感が求められます。
また、突発的なトラブルや工程変更が発生したときに、冷静かつ柔軟に対応できる人は、現場全体を落ち着かせることができます。現場の中心に立つ職長には、こうした「人間的な器」が何よりも重要です。
中堅層がキャリアの分岐点で考えるべきこと
20代後半〜30代後半の中堅層は、まさに職長候補としての適齢期にあたります。しかしこの時期は、「現場の最前線で、職人として手を動かし続けるか」「上の役割を目指すか」の岐路に立たされる時期でもあります。
そんな中で職長という選択肢は、自分の技術や経験を「人に伝える」ことでさらに高め、組織の中でより大きな裁量を持つキャリアのスタートでもあります。
- 手を動かす技術者として極めていく
- 現場を任されるマネジメント側に進む
この2つの道のうち、職長は後者の入り口です。未経験からでも「自分には人を動かす力があるかもしれない」と思ったら、まずは小さなリーダー的な役割にチャレンジしてみることが、次のキャリアにつながります。
経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月20日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
週休二日相当の休みやすさもあり、プライベートとの両立もしやすい職場です。
単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
まずは職場見学で現場を体感してみてください。後輩育成にやりがいを感じていた方、きっと共感いただける環境です。
詳しくは職長要項へ
職場見学・応募はこちら

未経験から職長を目指すための3つのステップ
現場作業員として経験を積む
未経験者が職長を目指す上で、最初のステップは「現場を知る」ことです。いきなり指示する立場にはなれません。
まずは作業員として現場に入り、基本的な業務や流れを体得することが重要です。建設現場の基本動作、安全ルール、資材の扱い方、工程管理の仕組みなどを、作業の中で自然と理解できるようになります。
ここで求められるのは「真面目に取り組む姿勢」です。以下のような行動は、職長候補としての第一歩につながります。
- 挨拶や小さなことでも報告を欠かさない
- 単純作業でも丁寧にやりきる
- 時間を守り、責任を持って行動する
- 先輩や上司の指示をよく聞く
現場の基本を理解し、信頼を積み重ねていくことで、次のステップに進む準備が整います。
小さなリーダー業務に挑戦する
ある程度の現場経験を積んだら、次は「部分的に現場を任せられる存在」になることを目指しましょう。最初から現場全体を管理するのではなく、少人数の指示や工程の一部を任されるケースから始まります。
たとえば以下のような業務です。
- 新人作業員への作業手順の説明
- 使用する資材や工具の準備と管理
- 作業スケジュールの確認と報告
- 危険箇所の指摘や注意喚起
これらの業務を「責任感を持って取り組めるかどうか」が重要です。現場の上司や周囲から「信頼できる」と判断されれば、自然と職長候補として意識されるようになります。
職長候補としての信頼を築く
職長を任されるかどうかは、「経験年数」や「年齢」よりも、「信頼されているかどうか」が大きく関係します。指示が的確でわかりやすいか、状況を冷静に判断できるか、人間関係を良好に保てるかといった点が重要視されます。
特に以下のような姿勢が信頼構築につながります。
- 作業に対して責任を持つ
- 問題が起きたときに逃げずに対応する
- 自分の失敗を隠さず報告する
- 他人のミスを責めるのではなく、カバーする
職長とは「任される存在」であり、「まとめ役」です。未経験であっても、こうした意識を持つことで、周囲から一目置かれる存在となり、職長の道が現実味を帯びてきます。
職長に求められるスキルと身につける方法
安全意識と観察力
職長として最も重視される能力のひとつが「安全管理」です。現場では小さな油断が大きな事故につながるため、常にリスクを予測し、未然に防ぐ意識が求められます。
安全意識を高めるためには、普段の業務中から以下の視点を持つことが効果的です。
- 作業員が無理な姿勢で作業していないか、不安全行動をしていないか
- 重機足場や資材の配置に危険はないか、危険の認識を持って作業しているか?
- 工具や重機の使い方に問題はないか
- 朝礼や終礼での安全指導内容を意識して行動できているか
これらを常に「見る」「気づく」習慣が観察力となり、現場を守る職長の土台となります。リスクに気づける人は、現場全体の安心感を生み出す存在です。
現場で必要なコミュニケーション能力
「コミュニケーション能力」と聞くと、話し上手・社交的な性格をイメージされがちですが、現場で必要なのはそれとは少し異なります。重要なのは、相手にわかりやすく、的確に伝える力と、相手の話をきちんと聞く姿勢です。
特に職長は、さまざまな立場の人と関わります。作業員、監督、協力会社、場合によっては発注者など、多方向への調整が発生します。トラブルの多くは「言った・言わない」「伝わっていない」ことが原因です。
- 指示は簡潔かつ明確に伝える
- 相手の反応を見て、理解度を確認する
- 困っていそうな人にはこちらから声をかける
- 意見の違いには一度受け止める姿勢を持つ
これらを日常的に意識するだけで、現場内での信頼度は格段に高まります。
柔軟な判断力とトラブル対応力
現場では想定外の出来事がつきものです。天候による工程変更、資材の納品遅れ、機材トラブル、人手不足など、常に変化が発生します。こうした中でも、状況を見て最善策を選べるかどうかが、職長に求められる資質です。
判断力を鍛えるには、日頃から「なぜこうなったか」「他にやり方はなかったか」と振り返る癖をつけることが効果的です。トラブル時に慌てず、複数の選択肢を頭に浮かべ、冷静に対応できる力は、経験と共に磨かれていきます。
また、失敗した時に「どうすれば次に活かせるか」を考える姿勢も、成長につながります。完璧な判断ではなく、柔軟で現実的な判断ができることが、信頼される職長への近道です。
職長を目指すなら知っておきたい講習・資格
職長・安全衛生責任者特別教育とは
建設業界で職長として現場を任されるには、「職長・安全衛生責任者特別教育」の修了が必要です。これは労働安全衛生法に基づいた法定講習で、作業員を直接指導・監督する立場になる前に受けなければならない教育です。
講習の主な内容は以下のとおりです。
- 現場におけるリスクアセスメントの考え方
- 安全衛生管理体制の構築と運用
- 指導方法と作業手順の作成方法
- 災害事例から学ぶ再発防止策
一般的には2日間で完了するコースが主流で、全国各地の建設業協会や安全衛生推進機関などで受講できます。
未経験者でも、現場である程度の経験を積んだ後であれば受講可能です。この講習を修了することで、職長として現場に立つ法的要件をクリアできます。
現場で有利になる技能講習や資格
職長になるには法定講習の修了が基本となりますが、それ以外にも持っておくと有利な資格・技能講習があります。実務で役立つだけでなく、職長候補としての信頼度も高まります。
たとえば、以下のような講習や資格が挙げられます。
- 玉掛け技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 車両系建設機械運転技能講習(解体等)
- 不整地車両運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- 地山・土止作業主任者技能講習
- 2級土木 or 建設機械施工管理技士(国家資格)
※17歳から第一次試験受講可能(令和6年4年 法改定) - 登録基幹技能士(機械土工)※10年以上の実務経験必要
特に施工管理技士は、将来的に現場監督や施工責任者を目指す場合の登竜門にもなります。資格は多く持っていればよいというものではありませんが、現場で必要とされるスキルとリンクした資格を選んで取得することで、評価に直結します。
eラーニングや通信講座の活用方法
最近では、講習の一部をオンラインで受けられるeラーニング形式の講座や、通信教育で学習できる教材も増えています。時間や距離の制約がある人にとっては、大きな味方です。
- スマホやPCでスキマ時間に受講可能
- 動画で作業手順や安全管理を学べる
- 模擬テストや確認問題で理解を深められる
- 紙のテキストとセットになった教材もあり
代表的な学習サービスとしては「SAT」などがあり、建設業界の資格取得をサポートする通信講座が人気です。現場経験を積みながら学びを深めるという“実務と学習の並走”が、無理のない成長につながります。
大切にする会社です!
職長のキャリアと年収:将来どうなる?
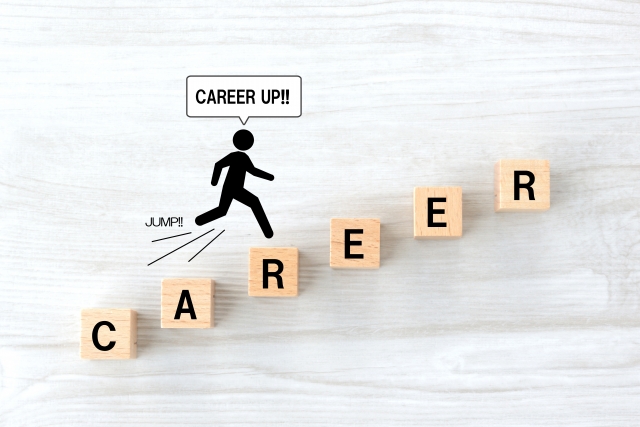 一般的な職長の年収・待遇
一般的な職長の年収・待遇
職長の年収は、業種や地域、所属企業の規模によって幅がありますが、建設業界においては平均年収400万~550万円程度が一つの目安とされています。特に公共工事を多く請け負う安定企業や、施工管理と兼任する職長などは、600万円を超えるケースもあります。
待遇面でも以下のようなメリットがあります。
- 月給制が多く、雨天などによる収入減少が少ない
- 資格手当や職長手当が支給されることが多い
- 管理職への昇進ルートが明確
- 評価制度により昇給しやすい仕組みがある
現場の“リーダー職”として評価されるポジションであるため、年齢や経験を重ねるほど収入も安定する傾向にあります。
キャリアアップの道筋(管理職・施工管理など)
職長を起点に、その先のキャリアをどのように築いていくかも重要です。職長の次のステップとしては、以下のような道があります。
- 施工管理職へのステップアップ(現場監督や現場代理人)
- 現場統括責任者(複数現場を統括する立場)
- 自営業・一人親方として独立
中でも施工管理技士(国家資格)を取得して施工管理者にステップアップする道は、待遇や裁量権の面で大きな魅力があります。
また、会社によっては管理職研修や評価制度を設けて、職長からステップアップするキャリアパスを明示しているところもあります。
地元勤務や働きやすさも重要な選択肢
キャリアを積むうえで、収入や役職と並んで重要なのが「働きやすさ」です。特に建設業界では、出張や長時間労働が避けられない職場も少なくありません。
しかし、地元密着で出張がほとんどない企業や、週休2日相当・年間カレンダー公開など、働き方を重視する企業も増えています。
働きやすさの指標となる要素には以下があります。
- 通勤範囲が限定されている(転勤・出張ほぼなし)
- 年間休日や有休取得実績が明示されている
- 月給保障など、収入面の安定策がある
- IT化やデジタルツール導入により作業負担が軽減されている
長く安定して働きながらキャリアを伸ばしたいと考えるなら、「地元で働ける」「制度が整っている」会社を選ぶことも、非常に現実的な判断といえます。
未経験から職長を目指すなら「育てる会社」を選ぼう
教育制度が整っている会社を選ぶ
未経験から職長を目指すなら、どの会社でキャリアをスタートさせるかが非常に重要です。特に、教育制度や研修体制が整っている会社は、成長のスピードと質が大きく変わってきます。
以下のような環境がある企業は、未経験者でも安心してスキルアップできます。
- 職長候補者向けの社内研修がある
- OJT(現場教育)体制が整っている
- キャリアプラン面談や成長支援制度がある
- 資格取得支援制度(講習費補助・受験料補助など)がある
育成体制が整っている会社は、「成長に時間がかかる人」を見捨てず、継続的にサポートする文化を持っています。これは、未経験者にとって非常に心強い環境です。
月給保障・評価制度の有無をチェック
現場作業において、天候や工事スケジュールの都合で仕事が中断することも珍しくありません。その際、日給制の場合は収入が不安定になる可能性があります。
その点、月給保障制度がある企業なら、雨天や工事停止時でも安定収入を維持できます。 特に家族がいる方や、計画的に収入を得たい方にとっては重要なポイントです。
加えて、以下のような制度の有無も確認しておくとよいでしょう。
- 職長手当や役職加算制度
- 評価制度による昇給・昇格機会の明確化
- 年1回以上の査定制度
- リーダー登用の基準が公開されている
収入とキャリアアップの両輪が揃っている会社であれば、目標に向かって迷わず進むことができます。
実績のある企業で信頼と経験を積む
最後に、会社の実績や評判も確認しておきたいポイントです。職長としての経験を積むには、「安定して仕事がある」「適正な規模の現場で学べる」ことが大前提です。
以下のような実績がある企業は、未経験者の成長機会が豊富です。
- 公共工事を安定的に受注している
- 地元密着型で継続的に案件がある
- 創業からの歴史や業界内評価が高い
- 離職率が低く、働きやすい文化がある
特に大和建設のように、育成実績が豊富で、地元のインフラを支える安定基盤を持つ企業は、未経験者が着実に職長を目指せる環境が整っています。
よくある質問(FAQ)
昇給・昇格の基準は会社によって異なりますが、一般的には担当した現場の規模や、安全管理・工程管理の評価、部下育成の実績などが重視されます。評価制度がある企業では、チェックリストや面談を通じて昇給が決定されることもあります。
班長はチーム内の実務管理が中心ですが、職長は現場全体の安全・進捗・人員調整を総合的に担うため、リーダーシップに加えて「調整力」や「多職種との連携スキル」が必要です。特に“全体を俯瞰する視点”が昇進の鍵となります。
職長としてのやりがいは、現場全体を安全・スムーズに動かし、予定どおりに工事が完了したときの達成感にあります。自分が計画した段取りがぴったりとハマったときには、「やっぱり自分の判断は間違ってなかった」と、自信がつくと話す職長もいます。
また、若手が自分の指導で成長したり、元請や管理者から「頼れる存在」と評価されたときにも、大きなやりがいを感じられるでしょう。
まとめ
未経験から職長を目指すことは、決して無謀な挑戦ではありません。
現場での経験を積みながら、周囲の信頼を得て、小さなリーダー業務から着実にステップアップすることが可能です。必要な講習や資格も、正しいタイミングで受講・取得することで、より確実にキャリアを前進させる土台となります。
特に重要なのは、自分を「育ててくれる会社」を選ぶことです。教育制度や評価制度が整っている職場であれば、努力がしっかりと報われ、目に見える形で成長を実感できます。
本記事で紹介した考え方や行動を参考に、ぜひ自分らしい働き方とキャリアを見つけてください。信頼される職長を目指して、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月20日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
週休二日相当の休みやすさもあり、プライベートとの両立もしやすい職場です。
単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
まずは職場見学で現場を体感してみてください。後輩育成にやりがいを感じていた方、きっと共感いただける環境です。
詳しくは職長要項へ

当社の重機オペレーターは、大規模な土木工事現場で活躍しています。
重機土工と呼ばれる仕事でブルドーザー・バックホウ・ダンプなど重機を使って土を「掘る・削る、運ぶ・動かす、敷き均す・盛る」土地や道路の基盤を作る工事全般の仕事です。
未開拓地や改良区画を大型重機で造成し、山間を一つ崩して平坦にしたり、姿カタチを変えてしまう魅力・醍醐味があります。
1日を通して重機を扱うため、始業時のカタチと終業時のカタチがまるで違うなんてことはいうまでもありません。
給与・福利厚生も仕事・技術内容に見合った安心して働ける充実な環境を用意。
難しい工事や危ない箇所で作業することも実際にはあります。
それでも「安全に・謙虚な前向きさと諦めない気持ち」を持って仕事できる方は向いていると思います。
大規模な工事現場で、一緒に新しい街づくりに携わる仲間を募集しています!

職場見学・応募はこちら

















