建設現場などでリーダー的な立場を担う「職長」になるには、資格が必要なのでしょうか?本記事では、職長に求められる教育の内容や、資格の有無が採用や昇進に与える影響についてわかりやすく解説します。
さらに、講習の流れや講座の選び方、将来のキャリアアップにどうつながるのかもご紹介します。これから職長を目指す方はもちろん、採用側にも役立つ情報をお届けします。

経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月20日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
週休二日相当の休みやすさもあり、プライベートとの両立もしやすい職場です。
単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
まずは職場見学で現場を体感してみてください。後輩育成にやりがいを感じていた方、きっと共感いただける環境です。
詳しくは職長要項へ
職場見学・応募はこちら
職長とは?現場で求められる役割と責任
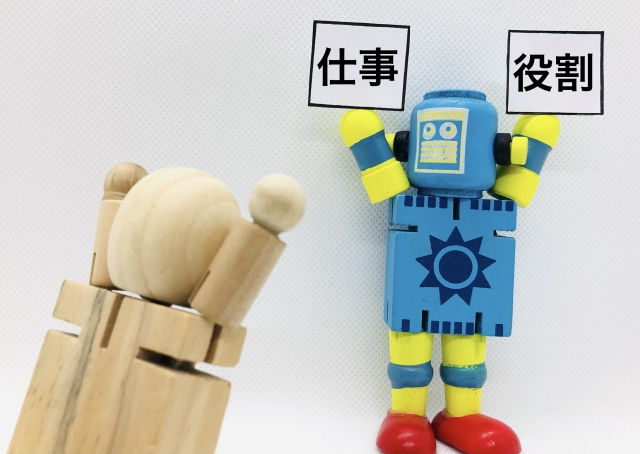
職長の基本的な役割とは
建設業や製造業の現場において「職長」とは、作業員を直接指導・監督する立場の人を指します。現場作業のリーダーとも言える存在であり、実務的な管理を任される重要なポジションです。
職長の主な業務は以下のようなものです。
- 作業員への指示や段取りの管理
- 工程や作業スケジュールの調整
- 安全衛生に関するルールの徹底
- 新人作業員や下請け業者の教育
- 災害防止に向けた指導と確認
単に作業を指示するだけでなく、「安全」や「品質」を守る役割も担っている点が特徴です。
職長は現場における“実質的な責任者”として行動が求められるため、リーダーシップや判断力、安全意識の高さが不可欠です。
なぜ現場に職長が必要なのか
現場での作業は常にリスクを伴い、複数の人が連携して進める必要があります。そのなかで、職長がいることで以下のような効果が期待できます。
- 危険の早期察知と回避(リスクアセスメント)
- チーム全体の統率と生産性の向上
- 作業手順の統一による品質の安定
- トラブル時の迅速な判断と対応
特に労働災害を未然に防ぐためには、職長の的確な指導と現場監視が極めて重要です。単なる中間管理職ではなく、「安全と生産の要」として企業からも高く評価される役割です。
次に、職長になるために「資格が必要か?」という疑問について詳しく解説していきます。
経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月20日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
週休二日相当の休みやすさもあり、プライベートとの両立もしやすい職場です。
単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
まずは職場見学で現場を体感してみてください。後輩育成にやりがいを感じていた方、きっと共感いただける環境です。
詳しくは職長要項へ
職場見学・応募はこちら

職長になるには資格が必要?採用・昇進に与える影響とは
「職長教育」は資格ではないが法的に義務化されている
まず結論から言うと、職長になるために特定の国家資格は必要ありません。 しかし、一定の条件下では「職長教育」の受講が法的に義務づけられています。
これは労働安全衛生法第60条および規則第40条に基づくもので、以下のような場合に教育の実施が義務づけられています
- 新たに職長として現場を指揮する立場に就くとき
- 作業内容に危険を伴う場合(建設・製造・解体など)
- 労働者を直接指導・監督するポジションに就くとき
したがって、職長になるには「資格」ではなく、「特定の教育の修了」が求められると理解することが重要です。
教育の受講歴が採用時の評価ポイントになる理由
求人票に「職長・安全衛生責任者教育修了者歓迎」と記載される例が増えています。理由は以下の通りです。
- 即戦力として現場に投入しやすい
- 安全衛生に関する意識と知識があると判断できる
- 教育実績のある人材は企業内での育成コストが低い
特に中途採用においては「教育を受けている=現場経験がある」と見なされる傾向があります。 未受講者に比べて書類選考や面接で有利になるケースが多いのが実情です。
昇進・昇格に影響するケース
社内での昇進においても、「職長教育の有無」が分岐点になることがあります。
例えば
- 現場作業員からリーダーに昇格するための前提条件
- 管理職手当や職長手当の支給基準
- 安全衛生委員会のメンバー選定要件
大手ゼネコンや公共工事を扱う企業では、教育修了が昇進基準として明文化されていることもあります。つまり、職長教育は「キャリアの通行手形」のような役割も果たしているのです。
次は、その「職長教育」とはどのような講習なのかを詳しく見ていきましょう。
職長・安全衛生責任者教育とは何か?【講習の内容と目的】
講習で学べる主なテーマ
職長教育では、単なる作業指示の方法だけでなく、現場での安全確保と労働災害の防止に焦点を当てた内容がカリキュラムに含まれます。講習で取り扱う主なテーマは以下の通りです。
- 危険予知(KY)活動とリスクアセスメント
- 作業手順の整備と周知
- 作業者への教育・指導のポイント
- 異常時対応・災害時対応の考え方
- 労働災害の原因と防止策
- コミュニケーションとチームマネジメント
これらは「知識」だけでなく「行動に移せる指導力」として習得が求められる内容です。
そのため、講義だけでなくグループワークやディスカッションを含む形式もあります。
労働安全衛生法に基づく受講義務
職長教育は労働安全衛生法(第60条)および規則第40条により義務づけられています。具体的には、以下のような立場の人に教育の実施が必要とされます。
- 作業班の指導者・班長・サブリーダーなど
- 労働者に対して直接的に業務指示を行う立場
- 危険を伴う作業(高所作業、解体作業など)の現場責任者
法令上の義務があるため、受講していないまま職長業務を担当させることは、企業としても法的リスクを抱えることになります。
一方で、この教育を修了していることは、現場での信頼性を高める「証明」としても機能します。
「職長教育」と「安全衛生責任者教育」の違い
この2つはまとめて行われるケースが多いですが、それぞれの目的には違いがあります。
| 教育の名称 | 主な目的 | 主な対象者 |
| 職長教育 | 作業の直接指導と監督方法を学ぶ | 現場リーダー、班長など |
| 安全衛生責任者教育 | 安全衛生に関する全体的な管理手法を学ぶ | 安全衛生の担当者、職長を兼ねる場合もあり |
両者を同時に受講することで、現場管理に必要な知識・スキルを総合的に身につけることができます。
次に、実際にこの講習をどのように受講すればよいのかを解説していきます。
大切にする会社です!
講習の流れと受講方法【受け方・費用・開催形式】
講習の日数と開催形式(対面・オンライン)
職長・安全衛生責任者教育は、原則として2日間(計12時間程度)のカリキュラムで構成されており、修了後には修了証が交付されます。
受講形式は以下の2パターンがあります。
- 対面形式(集合講習)
→ 多くの教育機関や民間団体で定期的に開催 - オンライン形式(eラーニング)
→ 一部団体で実施。自宅・職場から受講可能、時間の融通が利く
ただし、eラーニングの場合でも、最後に対面での確認講習(1日分)が求められることがあるため、申し込み時に詳細を確認することが大切です。
受講費用の目安と助成金の活用例
受講費用の相場は1人あたり10,000〜20,000円程度が一般的です。料金は実施団体や地域によって異なります。
中小企業や建設業者向けには、以下のような助成制度も存在します。
- 人材開発支援助成金(厚生労働省)
- 地域職業訓練センターの助成枠
- 労働災害防止団体の会員割引制度
法人単位での一括申し込みの場合は割引が適用されることもあるため、確認しておくと良いでしょう。
講習実施団体と申し込み方法
主な実施団体としては以下のような機関があります。
- 建設業労働災害防止協会(建災防)
- 一般社団法人全国労働安全衛生推進協会
- CIC日本建設情報センター
- 地方の労働基準協会・労働技能講習センター
申し込み方法はそれぞれの団体の公式サイトから行えます。日程や開催地の一覧が掲載されているため、事前に確認してから申し込むのがスムーズです。
続いては、こうした教育を受講することで得られるキャリア上のメリットについてご紹介します。
教育修了がキャリア形成に与える5つのメリット

現場での信頼獲得につながる
職長教育を修了していることは、現場において「安全や管理の知識がある人材」としての信頼を得るうえで重要です。作業員の安全を守るだけでなく、効率的な作業進行のためにも職長の判断力は不可欠です。
修了証の有無は、現場責任者や元請企業との関係性においても信頼材料になります。特に外部業者との共同作業では、教育を受けていることがスムーズな連携の鍵になります。
チームマネジメント力の向上
講習では、作業員への声かけや指示の出し方、チーム全体のモチベーション管理についても学びます。こうした内容は、実際の現場で応用しやすく、管理力のある職長として認められることにつながります。
以下のような変化を実感する人も多いです。
- 指示の出し方が明確になり、トラブルが減った
- 若手への指導に自信が持てるようになった
- 現場全体が落ち着き、作業効率が上がった
知識だけでなく、現場力の底上げにつながるのが教育の特徴です。
安全管理能力が評価される
労働災害の発生を未然に防ぐためには、危険予知やリスク評価の能力が求められます。職長教育ではこの点に重点が置かれており、受講後は日々の業務で安全に対する感度が高まります。
実際、教育修了者が現場にいることで次のような成果が見込めます。
- ヒヤリ・ハットの減少
- 問題発生時の初期対応が早くなる
- 安全書類や朝礼の質が向上する
このような実績は、企業としての安全水準を高めるだけでなく、発注者からの評価にも直結します。
資格手当など待遇アップの可能性
企業によっては「職長手当」や「安全管理手当」を設けており、教育修了者に対して毎月の給与に上乗せされるケースがあります。手当の有無は企業方針により異なりますが、評価項目に含まれていることは多いです。
さらに、以下のような待遇アップのきっかけにもなり得ます。
- 人事評価で加点対象となる
- 手当のあるポジションに選ばれやすくなる
- キャリア面談での交渉材料として有効
昇給や昇進といったキャリアの選択肢を広げる要素となります。
施工管理や監督職など上位職への道が開ける
職長は、施工管理技士や現場監督といった上位職へのステップでもあります。実際に、現場で職長経験を積んだのち、国家資格(例:1級・2級施工管理技士)を取得し、より上位の職務に就く人も少なくありません。
職長教育の受講は、その第一歩として企業側からも評価されやすく、社内での推薦や研修受講の対象になりやすくなります。
「教育 → 実務経験 → 資格取得」というルートが、長期的なキャリア形成の王道となっています。
大切にする会社です!
よくある質問(FAQ)
職長手当の金額は企業により異なりますが、一般的には月5,000円〜20,000円程度が相場とされています。現場の規模や責任範囲によって変動するため、求人票や社内規定を確認することが重要です。
職長・安全衛生責任者教育は、建災防や各地域の労働基準協会などで定期的に実施されています。受講料はおおよそ10,000〜20,000円で、助成金の対象になることもあります。開催形式は対面とeラーニングがあります。
職長として経験を積んだ後は、施工管理技士や現場監督など、さらに上位の管理職を目指すことが可能です。職長経験は国家資格受験の実務要件を満たすケースもあり、長期的なキャリア形成に有利です。
はい、職長経験者は建設業界での実務力があると評価され、中途採用市場ではニーズがあります。特に「職長教育修了済」や「安全衛生管理に携わった経験」があると、転職時のアピールポイントになります。
まとめ
職長として働くために国家資格は必要ありませんが、現場を安全かつ効率的に指導するための「職長教育」の受講は、法的に定められた重要なステップです。
この教育は単なる形式的な義務ではなく、現場力・安全管理力・チームマネジメント力を実践的に身につける機会でもあります。
また、職長教育の修了は採用時の評価ポイントとなり、昇進や資格手当、キャリアアップにも直結することがあります。特に中途採用や転職市場においては、現場経験と合わせて「教育済み」であることが強みとなります。
- これから職長を目指す方
- すでに現場経験があり、次のステップを考えている方
- 安全やマネジメントに課題を感じている現職の方
上記のいずれにの方にも、職長教育は「現場リーダーとしての実力」を証明し、自身の将来を広げる重要な機会となるでしょう。
経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月20日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
週休二日相当の休みやすさもあり、プライベートとの両立もしやすい職場です。
単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
まずは職場見学で現場を体感してみてください。後輩育成にやりがいを感じていた方、きっと共感いただける環境です。
詳しくは職長要項へ

当社の重機オペレーターは、大規模な土木工事現場で活躍しています。
重機土工と呼ばれる仕事でブルドーザー・バックホウ・ダンプなど重機を使って土を「掘る・削る、運ぶ・動かす、敷き均す・盛る」土地や道路の基盤を作る工事全般の仕事です。
未開拓地や改良区画を大型重機で造成し、山間を一つ崩して平坦にしたり、姿カタチを変えてしまう魅力・醍醐味があります。
1日を通して重機を扱うため、始業時のカタチと終業時のカタチがまるで違うなんてことはいうまでもありません。
給与・福利厚生も仕事・技術内容に見合った安心して働ける充実な環境を用意。
難しい工事や危ない箇所で作業することも実際にはあります。
それでも「安全に・謙虚な前向きさと諦めない気持ち」を持って仕事できる方は向いていると思います。
大規模な工事現場で、一緒に新しい街づくりに携わる仲間を募集しています!

職場見学・応募はこちら

















